
#13 菅野 秀さん
菅野 秀さん。
1987年生まれ。東京都葛飾区出身。
あらゆる同世代の“生き方”に触れる87インタビュー。
今回は、次世代パーソナルモビリティ「WHILL」を手がけるベンチャー企業の技術者(デザインエンジニア)として働く菅野さんを取材。
現在、最先端の技術を駆使した車椅子のデザイン・設計に取り組む背景には、一見、最先端のイメージとは対極に映る途上国「東ティモール」での経験がありました。
その経験をもとに生み出された「“両方”の最先端」を追いかける生き方とは?
菅野さんの価値観を形作った原点、そしてこれから目指す生き方に迫りました。
東ティモールで美術教育に挑戦!人生の中で「何をテーマとして持つべきか?」を考えさせられる

「先輩の知り合いが運営していて、僕がそういうの好きそうだったら『出てみない?』って声をかけてくれて」
そんな知り合いの一言がきっかけで出場した途上国向け適正技術開発コンテスト「See-D」。
東ティモールをテストフィールドとして「途上国の人が使いやすく、途上国の生活を快適にするデザイン・技術・サービス」を考えるビジネスコンテストだ。
そのコンテストで「途上国の農村地域にて画用木炭製造方法と美術教育を行う」というアイデアを提案し、学生最優秀賞を獲得。そのアイデアを現地で実践するベく、東ティモールに渡った菅野さん。
現地に渡って活動を続ける中で、思った以上に美術教育が行き届いていない現状を実感。
「『絵を描いてください』っていうお題を出すと、みんな同じ絵を描くんですよ。ちょっとバランスは違うものの、山があって、太陽があって、自分たちがよく知ってる家とかがあって、全員まったく同じ絵を描くんです」
美術教育は環境の整った先進国で行なわれている教育であり、途上国の環境にある東ティモールの子供たちは、自分で見たものを自由に発想して絵を描いた経験がない。そのため「見本の絵があると、みんながそれを真似して書いちゃう」という状態だった。
「僕はデザインと絵の勉強もやってきたので、『もっと人それぞれの自由な表現であるべきだ』という思いがあって。だから、見本の絵を真似して描くのではなく、目の前にあるモノを“感じたままに自由に描く”基本的な技法だったりとか、発想の方法だったりとかを伝える活動を行っていました」
そんな形でものづくりと美術教育を通して現地の人に貢献することに”やり甲斐”を感じ始めていた。しかし、プロジェクトが進むにつれて、様々なトラブルや資金面の理由から現地での活動を継続する難しさに直面する。
「現地の人々は基本的に受け身であることが多いので、僕らがいなくなってしまえばどんなに良い提案であってもその地で活動が継続されることはありません。継続するためには、如何に現地の人を巻き込むのかが重要なのですが、東ティモールに行って調査するだけで数十万かかってしまうため、資金的にかなり負荷が大きかったです。こういった現状でで『現地のひとのため』という思いだけで活動継続することの難しさを感じていました。
そのときの経験から「『誰かのため』というよりは『自分がおもしろいと思えること』や『やり甲斐を感じられること』、また『トラブルさえも面白いと思ってやっていけること』をテーマとして持つべきなのかなと感じました」
「僕自身は絵を描くのが好きだから、そういうのをテーマとして持つのも楽しいし、絵を描くのが好きな人が増えるのは面白いし。あえて真面目になりすぎないのも大事なのかなと」
東ティモールでの活動は、「やり切ったわけではない」と語るように煮え切らない思いも残った。
しかし、菅野さんにとっては、以後の選択に対して影響を与える大きな出来事となった。
ずっと探していた、美術と工学知識を結びつける「プロダクトデザイン」との出会い

東ティモールで美術教育に取り組んだ菅野さん。
美術や絵を描くことを好きになった原体験は保育園に遡る。
「保育園のとき、先生に描いた絵を褒められたのがきっかけですかね。小学生の頃は、図工と算数が好きな子供でした」
そんなこともあって中学生の頃には、将来「美術の先生になりたい」と考えるようになる。
「高校を経て美術を学べる大学に進んで、っていう進路を漠然と描いていたんです。ただ、高校入学直後に美大進学をテーマに開かれた講習会に参加した際『普通に美大に進んだとしても仕事がないかも・・・』という不安を感じてしまい、高校一年生ながらにショックを受けちゃったんです」
そんな出来事もあり、好きで得意な美術を活かして仕事をするイメージが持てず、一旦は得意な数学を活かして仕事になりそうな工学部に進む選択をする。
進学した大学で没頭したのは、授業よりも高校から続けていたダンスだった。
高校時代はメンバーとともに踊る創作ダンスの面白さにのめり込み、大学時代はブレイクダンスに熱中していた。
「大学3年まではもうダンスしかやってないじゃないかってぐらいサークルのダンスに打ち込んでましたね」
それでも、大学時代は「好きなダンスを『やってもやり足りないぐらい時間がある』と感じてました。大学の授業は楽しかったけど、『何かに向かって』授業を受けてる訳ではなかったんですよね」
ダンスサークルの活動自体は充実していた。だが、大学生活の中で流れていく時間に対し、どこか”物足りなさ”を感じていた菅野さんに転機が訪れたのは、3年生になったある日のこと。
「大学3年生の時、単位的にも余裕が出てきて、ふと『もう一回、美術の勉強できるんじゃないかな』って思ったんですよね。ただ、工学部で飛行機とかロケットを飛ばすための勉強をしてきて、かつ今からアートの勉強しても『何か意味あるのかな』」っと感じていたんです。その一方で、将来的に(工学部で得た知識とアートや美術の知識を)『うまく結びつけられる仕事』ってないのかなって探してて。結局『これだ!』って思ったのが『プロダクトデザイン』っていう分野だったんですよね」
「僕らが工学部で学んだのは『どうやってモノを作るのかだったり、どういう設計をするのか?』っていう分野。プロダクトデザインも全く同じで『この形をどういうふうな工法で作っていくのか』っていうのを考えながらデザインをやっていくっていう仕事。あっ!これでプロダクトデザインができれば、絵も描けるし、今まで勉強してきた工学部の知識も活かせるし『一石二鳥じゃん!』って思ったんです」
2つを結びつけるアイデアをひらめいた後、プロダクトデザインを学ぶために桑沢デザイン研究所へ通うことを決心する。
その当時は大学とのダブルスクール状態。そのため、大学の授業を終えると、夜間の授業を受けるために桑沢デザイン研究所へ直行する生活を2年間繰り返すことになったが、ようやく探していたモノを見つけ出せたことに嬉しさを感じていた。
「必要とされている場所」「思い描いた働き方」で、理想の仲間と一つの目標を追える環境へ

美術と工学知識を組み合わせてできることを探していた時期、「プロダクトデザイン」に辿り着くきっかけとなった出来事の一つが、大学3年生の時に知ったNPO団体の活動だった。
そのNPO団体は現在の働く会社の前身。普段、ソニーやオリンパスでテレビの設計や車の車載カメラを作ってるような一流メーカーのエンジニアたちが集まっていた。
そんなエンジニアたちが各々の仕事が終わった後にアパートの一室に集まり、普段の仕事とは別に「もっと社会貢献できるような製品を出して有志で発表する」という活動を行っていることを知り、刺激を受けた。 そしてなにより彼らの製品デザインがかっこよかった。
「すでに自分が思い描いたようなことをやってる人たちがいることを知ったから、将来的に『こういう仕事できるな』ってイメージできたんです」
桑沢デザイン研究所に通い始めてしばらくして、東ティモール向けのアイデアで出場した途上国向けコンテストで、偶然にも、そのNPO団体のメンバーと遭遇する。
偶然の出会いに驚いたが、そこで話したことをきっかけにNPO団体の活動も並行して手伝い始める。
しばらく一緒に活動しながらエンジニアたちと話しているうちに、「目の前の仕事や活動を心の底から好きな人は”本当に楽しそうに話す”」ことに気づいた。
その姿に影響を受けたことで、徐々に「自分のスキルとか技術力を上げるためにも、(将来的に)そういう姿勢の人たちと働きたいな」と考えるようになる。
また、彼らの姿を間近で見ていたことにより、エンジニアの業務を学んでおくことでプロダクトデザインの幅をさらに広げられると感じ、新卒の時は一旦、大手メーカーに就職。プリンターの設計を担当しつつ、エンジニアの仕事を現場で学ぶ。
新卒でメーカーで働く間も、仕事終わりにNPOの活動をずっと手伝い続けていた。
そのNPOが2013年に会社化。しばらくして資金調達の時期に「声をかけてもらい」、転職することを決意。
大手メーカーからベンチャー企業に移り、学生時代から影響を受け続けていたエンジニアたちと一緒の舞台で同じ目標を追いかけることになった。
「一緒に働けることになったメンバーたちも、僕の技術だったり、デザインだったりを良いと思って雇ってくれてると思うし、お互いに刺激し合える関係を保ててるのはすごく良かったかなと思います。今の会社には、デザイナーが僕と社長の二人しかいないこともあり、設計とデザインの両面において自分のまかされている領域の“重要性”と自分にしかできないという“必要性”を感じながら働けている」と語る。
また、「今の会社では、絵を描きながら、CADを使って設計するような働き方。そういう意味では、以前まで思い描いていた働き方を実現しているかもしれません」
決して順風満帆ではないが、東ティモールでの教訓を活かし、自分自身が本当に好きと思えるテーマを軸に活動を続けたことで、一歩ずつ理想の場所で理想の仲間と挑戦できる環境へと辿り着いた。
「世界の果てを見に行こう」一見、対極に見える“両方の最先端”を追う生き方とは?
「『これ両方最先端じゃん!だからどっちも取り組もう』と思ったんです」
東ティモールで画用木炭を製造する経験と、現在の仕事で最先端の車椅子を製造する経験。
一見、対極に見える技術に触れてきた菅野さん。しかし、そこにこそ技術への考え方と、これから目指す生き方が隠れていた。
「途上国向けに簡易の技術で画用の木炭を作るのも、インターネットと連携した車椅子を作るのも、技術的には『端っこと端っこ』だけど、そんなにかけ離れた話じゃない」
「僕自身、今の活動をやっていく中で『今の時代を生きるからには、最先端の技術の近くにいたい』という考えは常にあります。ただ、最先端の技術っていうと、よくロケットを飛ばしたりとか宇宙に行ったりとかっていう話を連想するんですけど(笑)例えば今、東ティモールの農村地帯に住んでる人たちはモノがなくて技術が届いてないんだから、そこに技術を届けるためには新しいアイデアとか技術とかが必要になるのは間違いない。だから、そっちも“最先端”と呼んでもいいと思うんですよね」
この他にも菅野さんは、一見関係ないように見えることでも、つなげて考える習慣がある。
プロダクトデザインに出会ったときも、一見かけ離れた美術と工学をつなげてできることを探し続けていた。
そして今も、仕事でプレゼンの構成を考えるときは(学生時代に熱中した)ダンスの構成を考える場面と重ね合わせて、より良い内容を模索している。
そういった経験を積み重ねていくうちに、その時々の一般的な視点だけに囚われず、自分なりの視点をつなげて考えることで何かが生まれる“面白み”に気づいた。
世界の果てと果て。
自身の経験から、両方の最先端をつなげて追いかけていくことに”新たな面白み”を見つけ出した菅野さん。
その先にどんな技術やプロダクトを生み出し、必要としている人々の元へ届けていくのか。
菅野さんの挑戦はこれからも続きます。
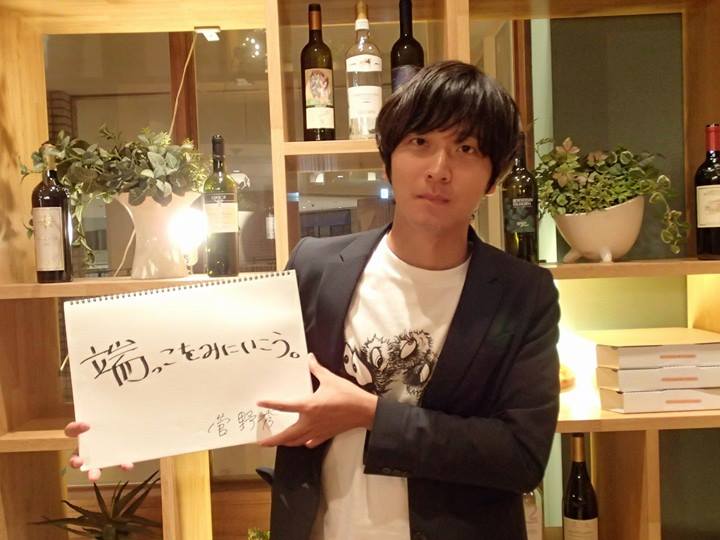
プロフィール
1987年生まれ。東京都葛飾区出身。
首都大学東京・大学院(航空宇宙工学)卒業。
高校時代は創作ダンス、大学時代はブレイクダンスに熱中する。
大学院時代、途上国向け適正技術開発コンテストSee-Dで学生最優秀賞を獲得。その受賞アイデアを、東ティモールにて画用木炭の製造や美術教育を普及させるプロジェクトを実施。
また同時期に、将来、得意な美術と工学知識を掛け合わせてできる仕事を探していた際に「プロダクトデザイン」と出会う。それを学ぶため、ダブルスクールで桑沢デザイン研究所に通う。
大学院卒業後、リコー株式会社にてプリンターの設計に従事。
その後、学生時代のSee-Dでの出会いをきっかけに手伝い続けていたNPO団体が「WHILL株式会社」として会社化されたのに伴い、同社に転職。
現在、WHILL社のデザインエンジニア兼サービス企画部門の責任者として、次世代パーソナルモビリティ「WHILL」のデザイン・開発・普及に取り組んでいる。
編集後記

「向こうの子供達に“将来の夢”を聞くと、3種類ぐらいしか出てこない。どんな仕事があるのか、自分の親しか見たことがないからイメージできなくて。それこそ海外に行くとこんな仕事があってとか、そこまで達しない。“知り得る術”が少ないんです」
東ティモールの子供たちと接した経験から、子供たちが視野を広げ、「将来やりたいことを知る」環境を作る大切さについて考えるようになった菅野さん。
今も業務の合間を縫い、子供たち向けに“ものづくりの面白さ”を体感できるワークショップに携わるなど、子供たちが将来の選択肢をイメージすることにつながる活動も行なっています。
そして昨年、第一子が誕生。一児のパパとなった菅野さん。
自分の子供や自身の活動を通じて携わる子供たちの存在も、これから更に菅野さんを前に進ませる原動力となりそうです。
(編集・撮影:87年会 編集部)


